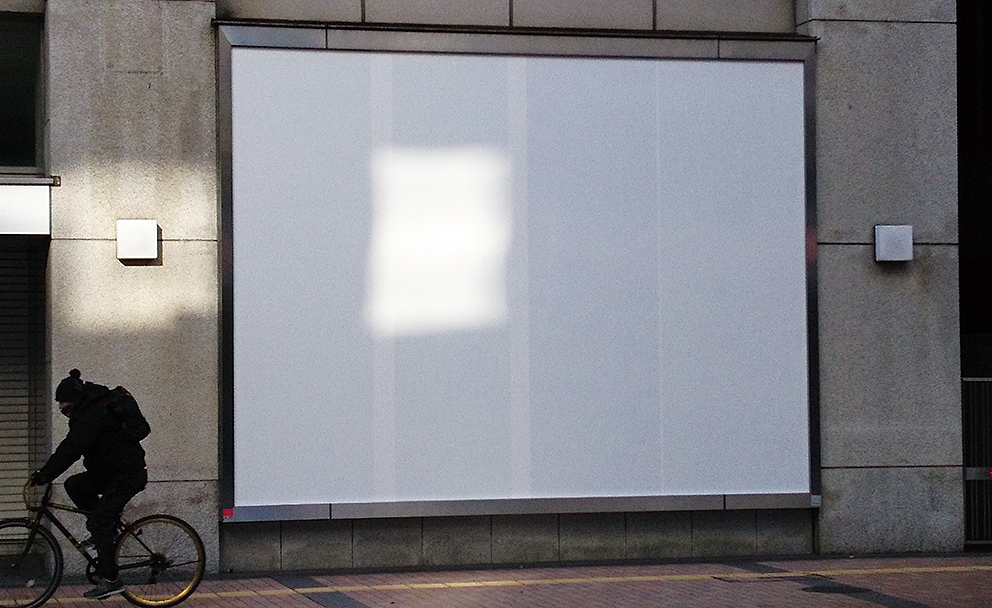元村正信の美術折々-2020-02
2020/2/25 (火)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
美術折々_258
全世界は正しいか
このあいだの昼下がり、屋根裏 貘の小田 満 氏とカウンター越しにいつもの芸術がらみの話をしていて僕の作品の話題になった。氏曰く元村の絵がレイ・ブラッドベリが書いたSF小説「火星年代記」で描かれた火星の光景に似ているというのだ。さっそく氏から借りて読んだが、そのような火星の美しくも廃墟化した山河や天空の
光景と僕の絵とは違うように思えたのだが。
それでも、いくつもの警句がちりばめられたこのSF小説の古典的名作は、70年前のものだが今だに人類にとっての科学と信仰の葛藤として読める。その中でもさりげなく書かれた次の言葉の重みはどうか。
〈全世界が正しいと思っているとき、一人の人間が正しいということはあり得るか〉。
僕にはズシンときた。ここにも信と不信の葛藤、人間の魂の救済は可能なのかと問われている。ただ僕はこれを芸術の価値への、作品の評価に対する問いとして受けとめた。すべての人が、そう「全てのひと」が、ある芸術をいいと思っているときに。世界に一人だけ、たとえば僕だけがそれはダメだと思う芸術は、あり得るのかと問うことができる。あるいはこう言い直すこともできる。世界のすべての人がダメだと思っている芸術を、だれか一人だけが、価値があると最後まで言い切れる芸術はあり得るのか、と。
レイ・ブラッドベリの警句は、だれもが異なる「ひとりの人間」であるはずなのに、なぜ地域の、社会の、国家の、世界の、といったフィクションつまり虚構や擬制のもとに同一化、多数化され正当化、正統化されたそれらが、さもあるかのような「人間」全体だとされるのかという問いと解釈することもできるのだ。さらにそれを「芸術」全体だと言うこともできるだろう。
しかし一度でも、たった「一人の人間だけが正しいということ」がもしあり得るとしたら、それは同時に「全世界」が否定されたことになる。つまり世界は成り立たなくなる。それは絶対的にあり得ないから、たった一人が正しいということはあり得ないという結論になる。だが、「だれもが異なるひとり」が真実なら、誰もがいつも「正しいたった一人」ということにはならないか。
だから僕は、レイ・ブラッドベリの問いかけにこう答えよう。
《全世界が正しいと思っているときでも、一人の人間だけがそれとは反対に正しいということは、
いつでもあり得る》と。じつは僕が「芸術」というものに期待していることは、こういうことなのだ。
もしかしたら小田 満 氏が 僕の絵を、ブラッドベリが描いた火星の光景に重ねて幻視したのは、
そういうことなのかも知れないと思った。
2020/2/17 (月)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
美術折々_257
「創造史」という近未来の見方
アーティストで東京造形大学特任教授の沖 啓介氏が、2月16日付 FBで 昨秋の改装で開館100周年を経た
ニューヨーク近代美術館のリポートをUPしていた。
それによると「今回は現代美術からさらに多様化している表現への変化を象徴し、空間のスケールは多様化、
複雑化し、従来の絵画や立体作品の間に映像、インスタレーション、建築、写真、デザインが入るようになり、美術史というより創造史へと認識を新たにしているように感じる」と報告している。
僕はこの「美術史というより創造史へ」という彼のあらたな受け止め方に興味を持った。これは当然のようにこれまで続いて来た特に近代から現代までの〈美術史〉という枠組や時間概念だけでは「作品」というものがまたその収集と展示が、もはや捉え切れなくなってしまっていることを実感してのことだと思う。
それを取り敢えずは「創造史」として呼ぶしかない、ということだろう。もちろんこれを単純に「芸術史」として括るわけにはいかないが。それでも沖氏が紹介するように、たとえば実験映画作家のマヤ・デレン(1917-1961)の映画が絵画の展示のなかにあったり、舞踏家のマース・カニンガム(1919-2009)のダンスも美術作品のなかにあったということを見ても、うなずける。
これだけでもすでに展示の中ですら「美術概念」もまた拡張、再編されているということになる。ただそれが
文字通りの〈創造〉としての捉え直しなのか、それとも〈美術史以後〉の表現の拡散と混迷そのものを「収集/
収拾」するためのものなのか。いずれにしろ、MoMAもまた「美術/芸術」の現在と近未来をまえに、
〈芸術以後〉にまでその射程をひろげようとしていることは確かだろう。
なお、沖 啓介氏のリポートには、氏の手による61点の写真も添付されている。
関心のある方は、FBでどうぞ。
2020/2/11 (火)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
美術折々_256
享楽と芸術の混濁の果て
かつてカントは、快適な技術を「享楽」といい、美的技術を「芸術」と言ってこのふたつを分け隔てたが。
いまはそう単純にはいかない。享楽にも美的技術はすみずみにまで浸透し、いっぽう芸術にも快適さの技術が
感覚が蔓延している。
たとえば昨年、森美術館で開かれ約66万人も動員した「塩田千春展:魂がふるえる」を見た椹木野衣が「会場が作家の思いなどと無関係に、てんでバラバラにインスタ映えする写真を撮るための一種の集合的な撮影スタジオと化している様を見て、批評の対象としての鑑賞はもはや極めて困難だと感じざるをえなかった」(『新潮』2月号)と言い、これを「無分別な傾向」だと語っていたが、極めて困難なのは何も「批評の対象として」だけなのではない。もはや「見る」ということ自体が、軽んじられ疎んじられているのだ。
でもこれに限らず、カメラ撮影OKの大規模展覧会なら、それが古典絵画や仏像であろうとどこも似たような現象である。展覧会というものが、じかに目で見る経験よりも、スマホで撮って楽しむ体験になったという訳だ。快感、快適さの情報化によって「鑑賞」もまた崩壊したのである。これこそが「娯楽」と「芸術」、つまり
エンターテインメントとアートの体験が情報化され、その区別がつかなくなっているということだ。
なぜ崩壊してしまったのか。それはひとつにはグローバルな自由化とういう名のあらゆる規制緩和がある。
法規制だって緩和すればするほど自由度は広がるが、そこに恣意は殺到し、弱肉強食はいっそう形を変え高度化する。価値が多様化したのではない。ひとつの価値というものが、より微細に刻まれ腑分けされ差別化されたその数だけ価値が生まれたように錯覚しているだけだ。一見新しい価値や自由を楽しんでいられるかに見えるが、
じつは真綿で私たちじしんの首を締めているということになるのである。
「享楽」の複雑化と「芸術」の脆弱化の相貌は、ますます見分けが付かないほど似てきている。
私たちはそんな享楽と芸術の混濁の果てに、いったいどんな光景を目にすることになるのだろう。
2020/2/5 (水)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
美術折々_255
鈍くかがやく光沢よ
昨年11月にアートスペース貘で写真家・津田 仁の個展「名のない時」をみて、欲しい作品があった。
いつもカネのない僕のこと。買えないので、元村の作品と交換するということでどうですか、と頼んでみよう。
そうおもい貘のオーナー小田さんを介してその旨を伝えてもらうと、津田さんから「いいですよ」とのうれしい
返事をもらった。彼がわざわざ自ら再度プリントし直してくれたのは、暮のこと。
あとはいつでも渡せます、ということだったのだが。
肝心の僕は、じぶんの作品を旧作から選ぶか新作にするかで迷う。
そうこうする内に年も明け、やっと1月も終わる頃に屋根裏 貘で津田さんに会え、遅そすぎた新作を渡し
目出度く交換あいなったしだい。
僕は気に入った写真を手にしたが、いっぽうの津田さんが僕の小品を気に入ってくれたかどうかは分からない。
彼は「いいですね」とは言ってくれたが、どうだろうか。いまもって不安は残ったままだ。お許しを。
津田 仁の写真「名のない時」から、この一点。
打ち捨てられた土地に鈍く光る一片あり。その向こうに山ありそのさらに遠く、また霞む山あり。
ここに転がるのは朽ちかけるものか、それとも光をたくわえ飛翔を待つものか。
そう何度もひとり反芻しながら。
これからそばに置いて、ながくじぶんの鏡にすることにしよう。
津田 仁「名のない時」2019.1204、
ゼラチン・シルバー・プリント
元村正信「抗い結晶するわたしたちの」
2020.0101、木製パネル・紙・アクリル
2020/2/1 (土)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
美術折々_254
見た夢でも 現実でもないもの
だれしも寝ている間に夢を見る。でも不思議なのは、その内容よりも眠っていて目をとじているのに、なぜ「見る」ことができるかということだ。
それは先天性盲目であっても、視覚を欠いた闇の中に記憶のような感触を体験しているという意味では、夢を見ていることに何ら変わりはない。
しかし「夢を見る」というけれど、現実には夢は「見た」ことの告白かその記述でしか語れない。脳科学者たちからすれば、それは目覚めた直後に脳内で再生、固定されそれを私たちが記憶するからだと言うが。僕の理解からすれば、つまり脳内の視覚野にはかつて何かを「見た経験」が(断片的あるいは統合、歪曲、合成されたものを含め)恣意的かつ曖昧あるいは鮮明に蓄積されていて、それを私たちは睡眠中に覗いているということになる。ただそれが意識としてか無意識によるものなのかは分からないが。
いずれにせよ脳の中には夢のようなものや、かつて見た記憶がつねに複雑に流動しシャッフルされていて、私たちが覚醒している間も目という視覚器官を介して外界の刺激を受容するだけでなく、逆にいまこの瞬間にも見ているものにそれらの記憶が重ねられ投影されているのかも知れない。見るということは、そう言うことなのだろうか。でもなぜ人の脳は夢という形を残存させて来たのだろう。そうしなければ現実という重みに耐えられなかったからだろうか。
夢うつつと言うが、この現在にあってもいま目の前に広がる風景や人も物も、そういった現実というものに逆流した脳内記憶がフィルターのようにかぶさっているのなら、自分がたったいま見ているものさえ不確かで曖昧なものに思えてくる。
記憶とは、けして過去だけのものではない。たえず歪められ忘却され断絶しながら現在的に内面化されるものであるなら。見るという経験は、同時にそんな記憶を呼び出す瞬間でもあるはずだ。見ることもそうやって歪められているのかも知れない。
たとえ夢と現実が、記憶という透明な皮膜を通して交わり語り合っているのだとしても、見るということの向こうにある、いまだ記憶なき無垢なる未知のものに、私たちはどこかで出合えないだろうか。夢とも現実ともことなるものに。
それには渋澤龍彦が言ったように「すべてをアレゴリー(寓意)とメタファー(隠喩)の中に解消して」しまうしかないのだろうか。