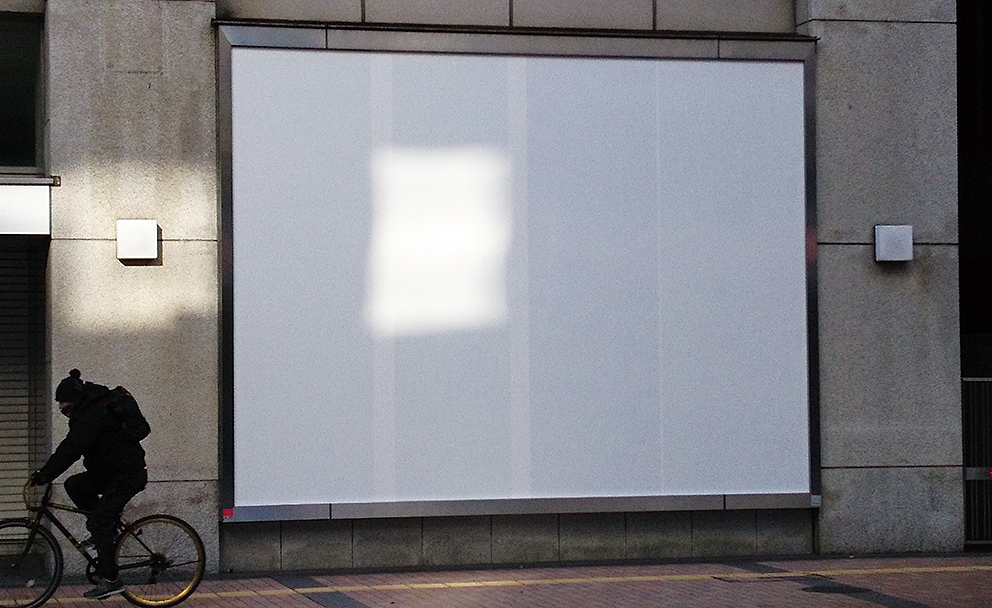元村正信の美術折々/2020-02-11 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 元村正信の美術折々/2020-02-11 へ行く。
- 1 (2020-02-11 (火) 20:15:31)
- 2 (2020-02-11 (火) 20:31:05)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
美術折々_256
享楽と芸術の混濁の果て
かつてカントは、快適な技術を「享楽」といい、美的技術を「芸術」と言ってこのふたつを分け隔てたが。
いまはそう単純にはいかない。享楽にも美的技術はすみずみにまで浸透し、いっぽう芸術にも快適さの技術が
感覚が蔓延している。
たとえば昨年、森美術館で開かれ約66万人も動員した「塩田千春展:魂がふるえる」を見た椹木野衣が「会場が作家の思いなどと無関係に、てんでバラバラにインスタ映えする写真を撮るための一種の集合的な撮影スタジオと化している様を見て、批評の対象としての鑑賞はもはや極めて困難だと感じざるをえなかった」(『新潮』2月号)と言い、これを「無分別な傾向」だと語っていたが、極めて困難なのは何も「批評の対象として」だけなのではない。もはや「見る」ということ自体が、軽んじられ疎んじられているのだ。
でもこれに限らず、カメラ撮影OKの大規模展覧会なら、それが古典絵画や仏像であろうとどこも似たような現象である。展覧会というものが、じかに目で見る経験よりも、スマホで撮って楽しむ体験になったという訳だ。快感、快適さの情報化によって「鑑賞」もまた崩壊したのである。これこそが「娯楽」と「芸術」、つまり
エンターテインメントとアートの体験が情報化され、その区別がつかなくなっているのだ。
なぜ崩壊してしまったのか。それはひとつにはグローバルな自由化とういう名のあらゆる規制緩和がある。
法規制だって緩和すればするほど自由度は広がるが、そこに恣意は殺到し、弱肉強食はいっそう形を変え高度化する。価値が多様化したのではない。ひとつ価値というものが、より微細に刻まれ腑分けされ差別化されたその数だけ価値が生まれたように錯覚しているだけだ。一見新しい価値や自由を楽しんでいられるかに見えるが、
じつは真綿で私たちじしんの首を締めているということになるのである。
「享楽」の複雑化と「芸術」の脆弱化の相貌は、ますます見分けが付かないほど似てきている。
私たちはそんな享楽と芸術の混濁の果てに、いったいどんな光景を目にすることになるのだろう。